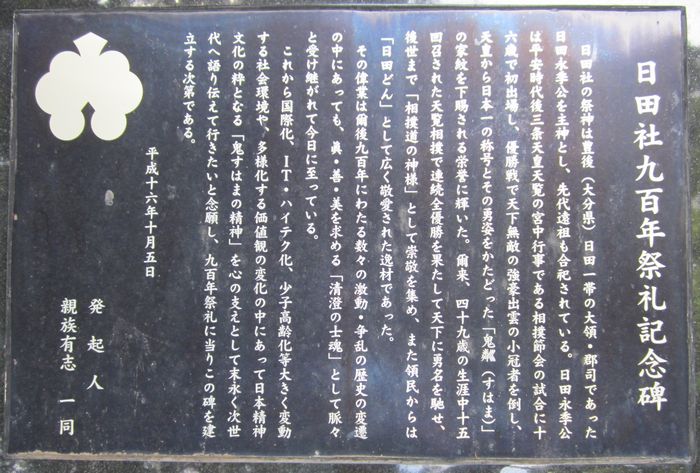239.藤崎八旛宮(ふじさきはちまんぐ)

熊本市内神社めぐり、9社めは藤崎八旛宮です。ここの参道も健軍神社ほどではありませんが、距離にして250m、長い参道が続いていました。私が到着した時に、楼門の前にトラックが2台停車し、神主さんがお払いをしていました。よく見ると、トラックの荷台にはそれぞれに馬が乗っていて、大きな帯のようなもので飾っています。聞いてみると、来週大祭があり、そのための安全祈願だということでした。楼門をくぐった中に拝殿、本殿があり、楼門からつながる廻廊で囲まれています。弊の外側には、たくさんの境内社が鎮座していました。通常八幡宮は「幡」の字すが、ここは「旛」の字を使います。これは、後奈良天皇の宸筆による勅額が「旛」の字になっていたため、以後、この字を用いたとのことです。後奈良天皇は間違えてしまったのでしょうか。
創建/由緒(ホームページより抜粋)
藤崎八旛宮は、承平5年(935)に朱雀天皇が平将門の乱平定を祈願され、山城国(京都)石清水八幡大神を国家鎮護の神として、茶臼山(今の藤崎台球場)に勧請されたのに始まる。鎮座の日、勧請の勅使が藤の鞭を3つに折って、3ヵ所に埋めたところ、この地に挿した鞭から、やがて芽が出て枝葉が繁茂したので、藤崎宮の名称が起こったと伝えられている。(藤崎八旛宮 社記による)
社名には「幡」ではなく、後奈良天皇宸筆の勅額に由来する「旛」の名が使われており、その姿は現在でも「大鳥居」に見ることができます。
戦国時代などには戦場となり、荒廃した時期もありましたが、朝廷から万民に至るまで広く信仰を集め、熊本総鎮守として崇められるようになっていきました。戦国から江戸時代には藩主となった加藤家、細川家により手厚く庇護されましたが、維新後の西南戦争で社殿が焼失。現在の井川渕町への遷宮が行われました。
その後、明治、大正、昭和、令和へと時代は変わりましたが、藤崎八旛宮は創建以来の変わることのない願いの心と共に、熊本の平安を見守り続けています。
御祭神
應神天皇(おうじんてんのう)(一宮)
住吉大神(すみよしのおおかみ)(二宮)
神功皇后(じんぐうこうごう) (三宮)
御神徳
武運長久・勝利の神・文化先駆・開発・諸業繁栄・国家鎮護・出世開運・厄祓い・海上渡航安全・交通安全・子宝・安産・育児
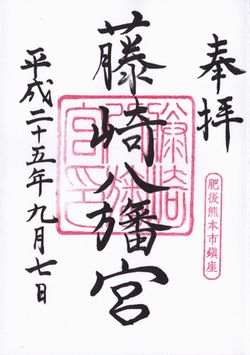










以下たくさんの境内社です。